そんな私が60歳になる頃、まさか建築士試験に挑戦するとは思いませんでした。
風水を“形にする力”を得るために、空亡という試練の時期をあえて選び、
一日14時間の勉強と図面地獄に向き合った記録です。
「老いは恥ではない」――そう言い切れる自分になるまでの、ちょっと遅い出発のお話。
60歳、建築士への挑戦―風水と人生の“空亡”を越えて―
「空亡に動く者は亡ぶ」…本当にそうなのか?風水では、「空亡(くうぼう)」の年に大きな決断をすると、
その行いはむなしく終わり、実を結ばないとされています。
12年に2年――誰にでも定期的に巡ってくる“氣の抜ける”時期。
けれど私は、あえてこの空亡期間に人生最大の挑戦を決意しました。
二級建築士試験への挑戦です。
なぜなら私は、風水を「思想」だけで終わらせたくなかったのです。
氣の流れを整えるには、間取りや構造に関わる“形の力”が必要。
宅地建物取引士の資格はもっており、不動産鑑定には力となる武器ですが、まだ何か足りないような気がしていました。
風水住宅を手掛ける者として足りない資格は、設計業務は必須だなと思っていたのです。
つまり、設計という実務の世界に入ることが不可欠でした。
それで空亡の2年に入ったところで、次の10年のために建築士という資格をチャレンジしてみよう。
合格できれば、風水師、宅地建物取引士、建築士のトリプルライセンス保有者になれるし、世の中には少ない風水建築士としてさらに飛躍できるかもしれない。
「老骨に鞭を打って走ってみるか!」

学科地獄篇:忘却と空腹と自己不信
建築士突破の決意から1年半の挑戦が始まりました。専門学校には通わず、完全独学を決意。
気合だけは満タン。だけど現実は――
・覚えたことは1時間後には霧散
・ノートを読み返して「誰が書いたんだこれ?」と他人事
記憶が脳にまったく定着していない
氣が整ってないのはむしろ自分の脳じゃないかと疑い出す
「このままでは口だけの人間になってしまうぞ。こうなったら朝の7時から夜9時まで14時間勉強しよう!」
重要な仕事、会食以外の外出、趣味は一切禁止としました。
食後は眠くなるので、こんなことでは合格できないぞと昼食は断食。
空腹ハイの状態で参考書を睨みつけ、
気づけばX(旧Twitter)で受験生たちの悲鳴ツイートを読みながら「同志よ…」とつぶやく日々。
「仕事もしないで…」と嫌味を言われても、
これは会社と未来のため。氣の通う住まいを次世代へ繋ぐ使命だ。
たしかに仕事の合間に勉強というより、勉強の合間に仕事しているというのが正しかったのです。
そんな環境を許してくれたことには感謝してもしきれないというところです。
そんな必死の状況で分かったのですが、歳を重ねると、若いときよりも遊びたいとかサボりたいとかの欲求が薄くなっているんですね。
睡眠もそんなに取らなくても案外いけるということは新たな発見でした。
廻りからはよくストイックにできるねと言われたりもしたのですが、案外辛さも感じず、これってたぶん高齢者特有の強みなんだなと思ったりしました。
フラフラして歩いていましたが、頭だけは冴えている感じ(苦笑)
そして、運命の学科試験当日――
試験内容は「計画」「法規」「構造」「施工」。合計6時間という耐久戦のような長丁場です。
会場に着くと、周囲の空気が異常にピリピリしている。
みんな最後の一秒まで参考書を読み、暗記カードをめくり、目が血走っている。
その光景を見て、私は思いました。
「うわぁ……みんな、ガチだ……。」
自分の頭の中には、よれた風船に覚えたことを目いっぱい詰め込みパンパンに膨れ上がっている。
こんな状態で針の一刺しでもあれば――全部パーンと覚えたことが破裂するんじゃないか。

そんな不安を抱えたまま、戦場のような試験が開始。
集中しすぎて、途中で自分の指が震えていることにも気づきませんでした。
そして試験終了の瞬間――
最後の問題にマークを塗り終えた瞬間、
腕から力が抜け、全身が椅子に溶け込むように脱力しました。
まるで、長い長いトンネルをようやく抜け出したような感覚。
「やれることは全部やった」
「人事を尽くしたのだから天命を待とう」
「これがダメなら……それはそれで、受け止めよう」
ふと、そんな言葉が心に浮かびました。
「もしこれで落ちたら、きっと神様が“お前は建築士に向いてないからやめとけ”って言ってるんだろう」
不思議と、怖くはありませんでした。
出し切ったという実感と、清々しいほどの満足感がありました。
合格の瞬間:静かに、しかし確かに込み上げた“人生初のガッツポーズ”
約2か月後。合否発表の日。インターネットで受験番号の確認ページを開く指は、驚くほど震えていました。
胸の鼓動がドクン、ドクンと腹の底に響く。
ここまで来た。やれることはすべてやった。
でも――“ダメかもしれない”という声が、どこかで囁いている。
静かにスクロール。
画面の中、数字の羅列に目を走らせていく。
……あった。
受験番号が、そこに、確かにありました。
その瞬間、身体の内側から、
抑えていた何かが一気にあふれ出してきました。
「よしっ……」
小さく、しかしこれまでの人生で最も強く、心を込めた“ガッツポーズ”が出ました。
大きな声ではなく、ゆっくりとしたうなずきと、拳に込めた万感の想い。
泣きました。
声にはならない涙です。
誰にも見られていないのに、なぜか背筋が自然と伸びていました。
この年齢になって、
「本気で嬉しくて泣く」
「自分を誇りに思える」
そんな瞬間が、まだ残っていたことに驚きました。
この歳で、人生が動いた
でも60歳になって、真正面から努力と向き合い、次の製図試験を受けてもいいぞというご褒美をもらった気がした。
それは、学科試験に受かったというだけではありません。
「過去の自分を超えた」という、人生の節目です。
今では、こう言いたい気分です。
「若い頃から冴えない人生送ってきた。今は挑戦してる。どちらも、立派な人生の一部じゃないか。」と。
製図地獄篇:図面の魔境へようこそ
学科試験に合格したからと言って喜んでいてはいけません。次に控えているのは、製図試験と言われる2次試験があります。
学科試験に受かっただけでは、建築士にはなれません。
学科試験を突破した者だけが製図試験を受ける挑戦権を得るのです。
学科試験に落ちた人は挑戦できないという仕組みです。
学科に受かった私は、思いました。
「よし、図面なんてパズルみたいなもんでしょ?」
「学科試験に比べれば図面を書くだけだから軽く突破できるでしょ!」と。
…今なら、その時の自分を1時間説教できます。
製図試験の内容は、5時間で1つの建物の設計図一式を描き上げるというもの。
その年の課題は「専門住宅」。
試験が始まるとまず課題文を熟読し、“エスキス(構想)”を練る。
試験が始まって初めて細かい諸条件が指示されるので、いかに早く構想をまとめるかが重要です。
ただ間取りを書けばいいのではなくて、最初に与えられた課題に則した図面を構想するのです。
構想した図面を一気に製図として以下を描き上げます:
各階平面図
立面図
伏図(梁などの構造図)
矩計図(断面詳細)
面積表
計画要点の記述
どれか一つでも書き漏らせば即失格。
文字どおり、一筆一筆が命取り。
5時間のうちに書き終わらないで終了という受験者が続出する過酷な試験。
「なるほど!なるほど!なんか想像してたことより大変そうだが、何とかなるでしょ!」
そういった試験内容だと頭で理解して、訓練スタート。
私の初回訓練――10時間かかっても完成せず。
腕は悲鳴、頭は真っ白。
朝からスタートしたのに夜になっても完成できない!

「これ、5時間で本当に書ける人間いるのか…?」
「これはまずいことになった!やはり無謀な挑戦だったか?」
Xを見て他の受験者の状況を調べてみることに。
そこには多くの製図挑戦者の阿鼻叫喚の悲鳴が書きこまれている。
「こんなの無理!書ききれる訳ない!」
「覚えることが多すぎる!」

「ほ~、自分だけじゃなさそうだ。若者も苦労してるぞ」
変な同士感を覚えて少し安心。
「だからといって自分は若者と違い、手も早く動かない。よし!若者の10倍努力して初めて土俵に乗れるはず。頑張ってみよう!」
毎日図面を描き続け、どの順番で線を書けば効率が上がるかを練り直し、道具の癖まで把握し、
やがて3時間以内に描き切れるように。
人間やれば無理と思っていたことも、継続すればできるようになる。
諦めることが一番よくないことだなと改めて感じます。

試験直前:図面依存症と、消えない不安
試験が近づくにつれて、生活はますます図面一色になっていきました。朝起きれば図面。夜寝る前にも図面。
スーパーのチラシすら“間取り図”に見えてくるほどの重症です。
試験1か月前からは、1日でも図面を描かないと落ち着かなくなるという“図面禁断症状”が出てきました。
「あれ?昨日図面描いてない…まずい、感覚が鈍る…」
「今日は平面図だけでもいいから描いておこう」
そんなことを毎日自問しながら、いつもシャーペンを握っていた日々。
もはや“図面を描く”という行為が、精神安定剤のような存在になっていました。
それでも、不安は常につきまとっていました。
「本番で何かミスをしたらどうしよう」
「想定外の課題が出たら、頭が真っ白になってしまうかもしれない」
「腕がつって動かなくなったら……?」
そうした思考が、布団の中で無限ループしていました。
眠っても夢の中でエスキスを描いていて、
起きた瞬間、「あの構成、意外といけるかも」と本気でメモを取った朝もありました(笑)。
試験会場で見たもの:若きライバルと自分
そして迎えた製図試験当日。会場に入ると、目に入ってきたのは――
若い受験者たちの真剣な表情。
机に静かに座り、シャーペンと定規の確認をするその姿に、
私は静かに思いました。
「きっと彼らの手は、自分よりもずっと早く動くんだろうな」
学科試験を突破した猛者達だけが、この試験場にいるわけで、みんな今まで必死に頑張ってきた同志。

60歳の私は、この場で最年長かもしれません。
「いやいや、逆に若者からしたら、自分のことを知識経験豊富なベテランがいると思ってるかもしれない」
「そうだ。きっとそう思っているはずだ!」

そう考えると、少し恐怖が消えた。
そして毎日の訓練が、確かな自信を残してくれていたから。
試験開始。
一斉に、紙をめくる音とシャーペンのカリカリという音が響く。
みんな、ものすごい集中力。
しかし、私は緊張と早く構想をまとめなければというあせりから、頭が真っ白寸前に。
「歳を取ってもやはり緊張するものなんだな。冷静に、冷静に・・」
深呼吸して耐え忍び、要求課題を読み込んで構想を検討して進めていきます。
1時間を過ぎた頃には、すでに作図を開始している受験者もちらほら。
一方の私はというと、エスキスに80分をかけました。
だが、それは想定内。自分のペースを崩さず、冷静に構成をまとめていく。
そこから迷いなく、手が動いた。
構図も、寸法も、手順も、すべてが訓練通り。
5時間が終わる少し前――私はすべての図面を描き上げていた。
解放の瞬間、そして静かな祈り
描き終えた瞬間、ペンを置いた私は、しばらく机の上を見つめていました。
それから、静かに背もたれにもたれ、深く、長く息を吐いた。
「もう、毎日図面を描かなくていいんだ」
「もう、全てのお誘いを断らなくていいんだ」
建築士挑戦決意から、誰かとの会食も断り、
旅行も控え、予定をすべて“訓練”に変えて過ごした日々。
その全てが、今、終わった――。
これ以上ないくらい、自分を出し切った。
できることは全てやった。
あとはもう、人事を尽くして天命を待つだけ。
60歳の手が描いた乾坤一擲の線たちが、どう評価されるのか。
それは、もう“氣の流れ”に任せるしかないのだと、
静かに思いました。

合格の瞬間:静かなガッツポーズと、騒がしい周囲
それから――季節が変わり、3か月後。ついに合格発表の日。
この試験は年に一度きり。
不合格なら、また1年間、あの図面漬けの日々が待っている。
ダメだったら、もう一度挑戦する覚悟はありました。
でも、家族にも会社にも、これ以上迷惑はかけたくない。
だからこそ、結果を見る瞬間は、
期待よりも、覚悟が勝っていたのかもしれません。
パソコンの前で、受験番号を確認。
……あった。
自分の番号が、そこにあった。
でも私は、声を上げませんでした。
胸の奥に静かに熱がこみ上げ、
わずかに口角が上がる。
ただ、それだけ。
「……あ~良かった。よし!」
人生で、これほど意味のある“よし”を言ったのは初めてかもしれません。
社内の騒ぎ、そして自分の中の静けさ
社内の人間にそっと報告しました。「…受かってしまったよ」
すると、なぜか私よりも向こうが騒ぐ。
静かに自分をかみしめていたその余韻は、社内に一言報告した瞬間、吹き飛びました。
「おおーっ!やったじゃないですか!」
「これで仕事してくれますね!」(皮肉?)
「いや〜、受かってくれて本当に助かった!」
周囲は嬉しそうに笑っていましたが、
その顔にはどこか「これで元の生活に戻れる」という安堵の色も混ざっていたような……。
私はそれを見ながら、心の中で思いました。
「ああ、これでようやく風水建築士として“実務”と“思想”の両輪が揃ったな」と。

空亡を越えて、次の10年へ ― 老いは恥ではない
風水では、「空亡」の時期に大きなことを決断しても、むなしく終わると言われます。確かに、氣が落ち着かず、思い通りに進まない時期です。
でも、私はあえてその空亡の2年間に挑戦することを選びました。
毎日図面を描き、眠気と空腹に耐え、
よれた風船のような記憶力と戦いながら――
60歳にして、これまでで一番「本気」だったかもしれません。
そして今、私は心から思います。
老いは恥ではない。むしろ、氣の本質に気づく力になる。
若いころは見えなかったものが、今は感じ取れるようになりました。
「ここに氣が滞っている」「この配置には違和感がある」
経験と感性が積み重なって、ようやく“形にできる氣”を扱えるようになったのです。
空亡の2年間で内なる氣を鍛え、整えた。
だからこそ、この先の10年は“氣が充ちる時間”になると確信しています。
「60歳で努力して合格」という話は、裏を返せば「それまで何をしてたの?」と受け取られてしまうかもしれません。
特に日本の社会は“遅咲き”に対して厳しかったり、過去の経歴で人を判断したりする傾向がありますよね。
でも、本当に重要なのは「過去」ではなく「今、何をしているか」。
そう、肉体は衰えてもスピリチュアルは永遠なのだから。
風水建築士として、これから
現在、私は、風水の思想と建築の実務を融合させた設計者として、住まいの氣を整えることを“天職”としています。図面は、単なる線の集合ではありません。
そこには、人の健康、家族の調和、財の流れ、そして心の静けさまでもが映し出される。
すべての運気は、線に宿り、形に流れ込むのです。
その流れを読み解き、整え、かたちに変える――
それが、私の仕事です。
人生の後半にようやく手にしたこの力を、
自分のためではなく、人のため、そして私の背中を見て、風水と言う素晴らしい理論を受け継いでいくだろう次世代のために使っていきます。
遅咲きでもいい。水を得た花が咲けば、風が香る。これぞ風水の氣!

株式会社パルナスのHPもご覧ください。

パルナスは笑顔の幸せ空間をご提案
HIROMI&YUKIKOの女性ならではの目線と心配りを大切にしたリフォーム、カーテンなど、幸せ空間のご提案・工事を得意としています。 また、不動産・建築・風水のプロであるNAO安藤が気軽に運をよくするインテリア風水から、土地や間取りから風...
問い合わせ、料金・サービスについて
お問合せはこちらのメールアドレスへ info@parnasse.jp
お電話で相談したい方は㈱パルナス 042-649-9907
お気軽にご連絡ください。
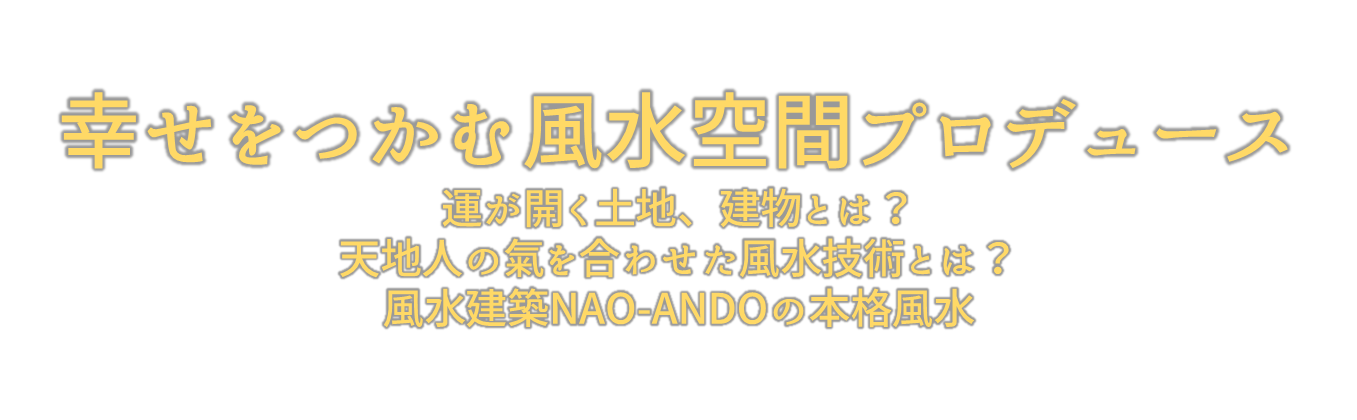


コメント