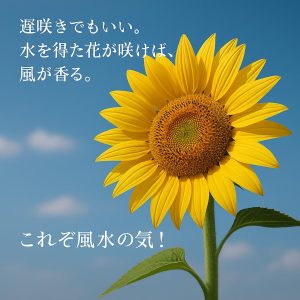風水建築士として活動する安藤尚尭が、実際の現場で学んできた視点から執筆しています。
旧石器時代の日本から今まで、どれくらいの人が人生を送ってきたのだろうか?
日本列島に人が住み始めたのは、約3万8千年前と言われています。
狩りをし、火を起こし、家族とともに暮らし、そして死んでいった――
そうした無数の命の営みが、私たちの足元に広がる大地には、長い時間をかけて積み重なってきました。
では、これまでにこの列島で人生を終えた人々の数は、どれくらいになるのでしょうか。
調べてみると、その数はおよそ13億人と推定されています。
今の中国の人口がすでに14億人を超えていることを思えば、
「たったそれだけなのか!案外少ないな。」と驚かされます。
3万8千年もの歳月を経ても、これまで日本で生き、死んでいった人々の総数が、
現代のたった一国の人口にも届かないのです。
そして、次の疑問が浮かびます。
その13億人の骨は、一体どこへ行ってしまったのだろうか。
ほとんどは風化し、土に還ったのだと思われます。
風雨にさらされ、土壌に溶け、やがて草の根の下へと消えていったのでしょう。
けれど、本当にそれですべてが終わったのでしょうか。
氣は? 意識は? 死者の痕跡は?
こうした素朴な疑問から、ひとつの思索を始めました。
風水と墓、死と氣、そして人がなぜ墓を建てたのか――
時代を越えて、静かに考えてみたいと思います。
第1章:墓を持たなかった人々 ――骨が還った土地
かつての日本において、墓を持つことはごく一部の特権階級に限られていました。
古代から中世にかけての庶民たちは、家ごとの墓を持たず、
死後は集落の外れや山の斜面など、村人たちが「穢れ地」として避けた場所に静かに埋葬されていました。
とくに南向きのなだらかな斜面が好まれていました。
湿気が少なく、風通しがよく、太陽の光がしっかりと届く。
こうした場所は、死者が安らかに眠れるようにという祈りとともに、
霊の祟りを避けたいという人々の素朴な配慮によって選ばれていたのでしょう。
そこで改めて考えてみると、このような地形は、現代においても“宅地開発に適した土地”と一致します。
なだらかで造成しやすく、南斜面で日当たりが良く、人里にも近いため利便性も高い――
だからこそ、今の住宅地の多くは、かつて人が静かに土に還ったその場所と重なっている可能性があるのです。

では、そうした場所に家を建てて住む現代の私たちは、
何か「氣」の影響を受けているのでしょうか?
この問いに対して、ふと思い当たることがあります。
「そういえば、昔の埋葬地の上に家を建てたからといって、
霊の祟りや怪異が頻繁に起きたという話は、あまり聞かない。」
この現象は不思議です。
本当に霊が残るのであれば、こうした場所でこそ何かが起こってもおかしくないはずです。
それなのに、なぜ静かな土地として、家族が安心して暮らせているのでしょうか。
風水的な見方では、そこに「氣の質」という考え方が存在します。
かつてそこに埋葬された人々の多くは、
戦で無念の死を遂げた者でもなければ、怨みを抱いて命を落とした者でもありません。
寿命を全うし、家族に見送られ、静かに土に還った者たち――
つまり、その場所に染み込んだ氣は「穏やかな氣」「自然に還る氣」であると考えられるのです。
そうした氣は、時が経てば自然の氣と溶け合い、
やがては静かな“陰の氣”として土地に沈んでいきます。
そこに陽の氣(太陽の光や人の暮らし)が加わることで、むしろ穏やかで安定した場所になることもあるのです。
もちろん、すべての土地がそうだとは限りません。
処刑場や戦場、供養されないまま埋葬された無縁仏の地など、
強い恨みや苦しみを抱えた魂が眠る場所では、異なる氣の作用があるかもしれません。
しかし、日本各地の自然な埋葬地に関しては、
多くが「恨みのない氣」の上に重ねられており、
それが現代においても土地の静けさや住みやすさとして表れているのかもしれません。
第2章:骨は消えても、氣は残るのか
風水において、骨は“氣の本体”ではありません。 それは、生きていたときの氣のエネルギーの凝縮された残骸であり、 魂が離れたあとの名残として、しばらくの間その土地に影響を与えると考えられています。
けれど、それは“魂そのもの”ではありません。魂とは、意識であり、感情であり、記憶であり、個としての存在です。もし魂が本当に存在するのであれば、それは仏教や道教が説くように、死後、輪廻転生していくはずです。
つまり、時間が経てば経つほど、その魂はすでに新たな生を受けており、かつての「霊」としてそこに留まっている理由がなくなっていくのです。
魂は精神的・陽的な性質を持ち、天に昇るとされ、
魄(骨)は肉体や本能に結びついた陰の性質を持ち、地に留まるとされます。
(『荘子』『淮南子』などに見られる思想)
骨が持つ氣は時間とともに風化し、霊的な影響もまた静かに薄らいでいきます。
それはまるで、土地に宿った氣が、やがて場に溶け込んでいくようでもあります。
どんな氣も永遠ではない。風水もそれを前提に成り立っているのです。
これを裏付けるような話があります。たとえば、古戦場と呼ばれる場所――関ヶ原や戦国の合戦地では、かつて「霊が出る」と恐れられた場所も、近年ではそうした話をあまり聞かなくなりました。
もちろん、その土地の氣の重さが完全に消えたわけではありません。しかし、そこに宿っていた“意識”としての霊たちは、輪廻の中で再び人として生まれ変わっていったと考えれば、静かになっていくのも納得がいきます。
このように、骨は氣の容れ物ではあっても、魂ではない。 時間と共に氣は自然に薄まり、魂は転生していく。 そう考えることで、私たちは土地に対して、過剰な恐れや神秘主義から一歩距離を置くことができます。
そして、それでも人は、死者のために墓を建て、土地の氣を整えようとする。 それは、魂のためというよりも、残された者のため――すなわち、“生きている人”のための行為なのかもしれません。
第3章:氣の力を王朝に宿す ――徳川家の風水墓
人はなぜ、墓を建てようとするのでしょうか。
それは、死者を祀るためだけではありません。
そこには、死者の氣を土地にとどめ、次の世代へと良い影響を残したいという、
人間の本能的な祈りが込められているのかもしれません。
庶民がようやく墓を持てるようになったのは比較的近代に入ってからですが、
それ以前の歴史では、墓を建てること自体が権力者や支配層に限られた特権でした。
なぜなら、墓は単なる“弔いの場”ではなく、
風水的に氣を集め、家系や王朝の繁栄を支える「氣の装置」と見なされていたからです。
権力者たちは、自らの氣が凝縮された骨を墓に保存して、「死してなお氣を発し」、
子孫や国家を護りたいと願ったのです。
風水は、そのための天地の理(てんちのことわり)を読み解く技術でもありました。
中国の王朝や日本の徳川幕府は、そうした風水の思想を都市や墓づくりに取り入れ、
氣を国家経営に活かそうとした代表的な事例です。
権力者にとって家系を守るとは、単に血を繋ぐことではありませんでした。
とくに功績を残した先祖の氣を、墓を通じて継承し、そこから家運を支えようとしたのです。

第4章:骨も氣も消える ――それでも人は繁栄を託す
風水で墓を建てたとしても、家が永遠に続くとは限りません。
骨はやがて風化し、氣も少しずつ薄れていきます。
実際、日本のような湿気の多い土地では、
土に埋めた骨は数百年のうちにほとんど消えてしまいます。
たとえ火葬された骨であっても、
骨壺が割れたり、湿気で崩れたりして、失われることがあります。
つまり、どれほど立派な風水墓を作ったとしても、
その氣の元となる骨は、いずれ形を失ってしまうということです。
風水の発祥である中国でも漢(前漢+後漢)が約426年、日本の徳川幕府が約270年。
歴史を見ても風水の効果が永遠ではないこともわかります。
それだけではありません。
家系が続かなくなるもう一つの大きな原因――それは、子孫の側にあります。
どれだけ良い氣を受け継いでも、
それを活かす人間が欲にまみれたり、先祖を忘れたりすれば、
氣は濁り、家は衰えていきます。
これも中国王朝や日本を見ても、皇帝や官僚の腐敗政治、権力欲しか考えない政治がはびこるようになると滅亡が近くなるようになります。
風水は氣を整える術ではありますが、人間の心までは整えることは出来ません。
だから、家を守るためには、氣とともに徳(生き方)も受け継がれていく必要があるのです。
この子孫の心の問題は風水の守備範囲ではありません。
あくまで、子孫の良心が基礎にあっての風水なのです。
だからこそ、風水は万能ではありません。 しかし、それを理解したうえで、限られた時間の中で氣を整えるために使うならば、 これほど力強く、意味のある智慧はないとも言えるでしょう。
そしてもう一つ、家を長く守っていくうえで大切な視点があります。
それは、氣は消えるが、志によって再び整え直せるということです。
どの家系にも、長く続く家には“志を継いだ人物”が途中の世代で現れます。
そうした人物の存在が、家に新たな氣の流れをもたらし、
それまでに弱くなった氣を、再び整える中心軸となることがあるのです。
歴史には、偉人の墓が時代を越えて中興の祖として祀られ直され、
その志を受け継いだ子孫や門下が再び繁栄するという例が少なくありません。
つまり、氣が薄れたときこそ、
“誰の志を継ぐか”“誰を中心に祀るか”を見直すことで、風水はもう一度命を吹き返すのです。
終章:それでも人は整えようとする
骨は風化し、氣はやがて薄れていきます。
家系は続くとは限らず、風水も永遠を保証するものではありません。
私たちは、それをもう知っています。
それでも人は、墓を建て、
風水でその場所を整えようとします。
そこには、理屈を超えた静かな願いがあるのだと思います。
せめて今を、
そして次の世代を、
少しでもよい氣の中で生きてもらいたい――
そんな思いが、墓というかたちになり、
風水という知恵として受け継がれてきたのでしょう。
風水は、氣を整える技術でありながら、
実は“生きている人間の心を整えるための鏡”のようなものかもしれません。
墓の配置、氣の流れ、風の通り道、水のたまり――
それを整えることで、
私たちは自分の在り方を問い直しているのかもしれません。
すべてが消えていくと知りながら、
それでも人は、整えようとする。
その姿勢こそが、
人間が人間らしく在るための、ひとつの祈りなのだと思います。
風水は、永遠をつくるための魔術ではありません。
それは、限られた時間の中で氣を整えようとする人間の、美しい生き方なのです。
最後に
一体何人の日本人がこの日本で人生を送ったのだろうという素朴な疑問から、歴史、宗教、風水などを紐づけて考えてみました。
旧石器時代から38000年続く1億4000万人の1人。たまにはこんなことを考えるのも悪くないですね。最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事は、風水建築士・安藤尚尭が執筆しています。
風水と建築の融合をテーマに、設計・現場・鑑定を一貫して手がけています。
📚 もっと風水について知りたい方へ:
📢 株式会社パルナスでは、お問い合わせ・ご相談を2つの方法で承っております:
▶ 株式会社パルナス 公式ホームページを見る
▶ メールで問い合わせる
▶ 電話で相談する(042-649-9907)